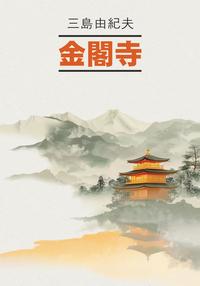Золотой храм / 金閣寺
Книга для чтения на японском языке
Покупка
Издательство:
КАРО
Автор:
Мисима Юкио
Год издания: 2024
Кол-во страниц: 352
Дополнительно
Вид издания:
Художественная литература
Уровень образования:
Дополнительное образование
ISBN: 978-5-9925-1828-3
Артикул: 850709.01.99
«Золотой Храм» — самое известное произведение японского писателя Юкио Мисимы. Оно основано на реальном факте: в 1950 году монах сжег Золотой Храм в Киото — и этот разрушительный эпизод настолько впечатлил
Мисиму, что тот решил написать свою версию события. Философский роман с тонкой восточной созерцательностью, живописными пейзажами и красочными метафорами рассказывает о поиске красоты в этом мире — и невозможности обрести Прекрасный идеал. Молодой монах Мидзогути, с детства восхищающийся образом Золотого Храма, посвятил жизнь поиску того самого идеала. Но порой стремление к гармонии с внешним миром приводит к
роковым последствиям…
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
三島由紀夫 金閣寺
УДК 811.521 ББК 81.2 Яп-93 М65 Мисима, Юкио. М65 Золотой Храм : книга для чтения на японском языке / Юкио Мисима. — Санкт-Петербург : КАРО, 2024. — 352 с. — (近現代文学). ISBN 978-5-9925-1828-3. «Золотой Храм» — самое известное произведение японского писателя Юкио Мисимы. Оно основано на реальном факте: в 1950 году монах сжег Золотой Храм в Киото — и этот разрушительный эпизод настолько впечатлил Мисиму, что тот решил написать свою версию события. Философский роман с тонкой восточной созерцательностью, живописными пейзажами и красочными метафорами рассказывает о поиске красоты в этом мире — и невозможности обрести Прекрасный идеал. Молодой монах Мидзогути, с детства восхищающийся образом Золотого Храма, посвятил жизнь поиску того самого идеала. Но порой стремление к гармонии с внешним миром приводит к роковым последствиям… УДК 811.521 ББК 81.2 Яп-93 ISBN 978-5-9925-1828-3 © КАРО, 2024 Все права защищены
第一章 幼時から父は、私によく、金閣のことを語 った。 私の生れたのは、舞鶴から東北の、日本海へ突 き出たうらさびしい岬である。父の故郷はそこで はなく、舞鶴東郊の志楽である。懇望されて、僧 籍に入り、辺鄙な岬の寺の住職になり、その地で 妻をもらって、私という子を設けた。 成生岬の寺の近くには、適当な中学校がなか った。やがて私は父母の膝下を離れ、父の故郷の 叔父の家に預けられ、そこから東舞鶴中学校へ徒 歩で通った。 父の故郷は、光りのおびただしい土地であっ た。しかし一年のうち、十一月十二月のころに は、たとえ雲一つないように見える快晴の日に も、一日に四五へんも時雨が渡った。私の変りや すい心情は、この土地で養われたものではないか と思われる。 3
五月の夕方など、学校からかえって、叔父の 家の二階の勉強部屋から、むこうの小山を見る。 若葉の山腹が西日を受けて、野の只中に、金屏風 を建てたように見える。それを見ると私は、金閣 を想像した。 写真や教科書で、現実の金閣をたびたび見なが ら、私の心の中では、父の語った金閣の幻のほう が勝を制した。父は決して現実の金閣が、金色に かがやいているなどと語らなかった筈だが、父に よれば、金閣ほど美しいものは地上になく、又金 閣というその字面、その音韻から、私の心が描き だした金閣は、途方もないものであった。 遠い田の面が日にきらめいているのを見たり すれば、それを見えざる金閣の投影だと思った。 福井県とこちら京都府の国堺をなす吉坂峠は、丁 度真東に当っている。その峠のあたりから日が昇 る。現実の京都とは反対の方角であるのに、私は 山あいの朝陽の中から、金閣が朝空へ聳えている のを見た。 こういう風に、金閣はいたるところに現われ、 しかもそれが現実に見えない点では、この土地に おける海とよく似ていた。舞鶴湾は志楽村の西方 一里半に位置していたが、海は山に遮ぎられて見 えなかった。しかしこの土地には、いつも海の予 4
感のようなものが漂っていた。風にも時折海の匂 いが嗅がれ、海が時化ると、沢山の鴎がのがれて きて、そこらの田に下りた。 体も弱く、駈足をしても鉄棒をやっても人に 負ける上に、生来の吃りが、ますます私を引込思 案にした。そしてみんなが、私をお寺の子だと知 っていた。悪童たちは、吃りの坊主が吃りながら お経を読む真似をしてからかった。講談の中に、 吃りの岡っ引の出てくるのがあって、そういうと ころをわざと声を出して、私に読んできかせたり した。 吃りは、いうまでもなく、私と外界とのあい だに一つの障碍を置いた。最初の音がうまく出な い。その最初の音が、私の内界と外界との間の扉 の鍵のようなものであるのに、鍵がうまくあいた ためしがない。一般の人は、自由に言葉をあやつ ることによって、内界と外界との間の戸をあけっ ぱなしにして、風とおしをよくしておくことがで きるのに、私にはそれがどうしてもできない。鍵 が錆びついてしまっているのである。 吃りが、最初の音を発するために焦りにあせ っているあいだ、彼は内界の濃密な黐から身を 引き離そうとじたばたしている小鳥にも似てい る。やっと身を引き離したときには、もう遅い。 5
なるほど外界の現実は、私がじたばたしているあ いだ、手を休めて待っていてくれるように思われ る場合もある。しかし待っていてくれる現実はも う新鮮な現実ではない。私が手間をかけてやっと 外界に達してみても、いつもそこには、瞬間に変 色し、ずれてしまった、……そうしてそれだけが 私にふさわしく思われる、鮮度の落ちた現実、半 ば腐臭を放つ現実が、横たわっているばかりであ った。 こういう少年は、たやすく想像されるように、 二種類の相反した権力意志を抱くようになる。私 は歴史における暴君の記述が好きであった。吃り で、無口な暴君で私があれば、家来どもは私の顔 色をうかがって、ひねもすおびえて暮らすことに なるであろう。私は明確な、辷りのよい言葉で、 私の残虐を正当化する必要なんかないのだ。私の 無言だけが、あらゆる残虐を正当化するのだ。こ うして日頃私をさげすむ教師や学友を、片っぱし から処刑する空想をたのしむ一方、私はまた内面 世界の王者、静かな諦観にみちた大芸術家になる 空想をもたのしんだ。外見こそ貧しかったが、私 の内界は誰よりも、こうして富んだ。何か拭いが たい負け目を持った少年が、自分はひそかに選ば れた者だ、と考えるのは、当然ではあるまいか。 6
この世のどこかに、まだ私自身の知らない使命が 私を待っているような気がしていた。 ……こんな一挿話が思い出される。 東舞鶴中学校は、ひろいグラウンドを控え、 のびやかな山々にかこまれた、新式の明るい校舎 であった。 五月のある日、中学の先輩の、舞鶴海軍機関 学校の一生徒が、休暇をもらって、母校へあそび に来た。 彼はよく日に灼け、目深にかぶった制帽の庇 から秀でた鼻梁をのぞかせ、頭から爪先まで、若 い英雄そのものであった。後輩たちを前にして、 つらい規律ずくめの生活を語った。しかもそのみ じめな筈の生活を、豪奢な、贅沢ずくめの生活を 語るような口調で語ったのである。一挙手一投足 が誇りにみちあふれ、そんな若さで、自分の謙譲 さの重みをちゃんと知っていた。彼はその制服の 蛇腹の胸を、海風を切って進む船首像の胸のよう に張っていた。 彼はグラウンドへ下りる二三段の大谷石の石段 に腰を下ろしていた。そのまわりには、話に聴き 惚れている四五人の後輩がおり、五月の花々、チ ューリップ、スイートピイ、アネモネ、雛罌粟、 などが斜面の花圃に咲きそろっていた。そして頭 7
上には、朴の木が、白いゆたかな大輪の花をつけ ていた。 話者と聴手たちは、何かの記念像のように動かな かった。私はといえば、二米ほどの距離を置いて、 グラウンドのベンチに一人で腰掛けていた。これが 私の礼儀なのだ。五月の花々や、誇りにみちた制服 や、明るい笑い声などに対する私の礼儀なのだ。 さて、若い英雄は、その崇拝者たちよりも、よ けい私のほうを気にしていた。私だけが威風になび かぬように見え、そう思うことが彼の誇りを傷つ けた。彼は私の名をみんなにきいた。それから、 「おい、溝口」 と、初対面の私に呼びかけた。私はだまったま ま、まじまじと彼を見つめた。私に向けられた彼 の笑いには、権力者の媚びに似たものがあった。 「何とか返事せんのか。唖か、貴様は」 「ど、ど、ど、吃りなんです」 と崇拝者の一人が私の代りに答え、みんなが 身を撚って笑った。嘲笑というものは何と眩しい ものだろう。私には、同級の少年たちの、少年期 特有の残酷な笑いが、光りのはじける葉叢のよう に、燦然として見えるのである。 「何だ、吃りか。貴様も海機へ入らんか。吃 りなんか、一日で叩き直してやるぞ」 8
私はどうしてだか、咄嗟に明瞭な返事をした。 言葉はすらすらと流れ、意志とかかわりなく、あ っという間に出た。 「入りません。僕は坊主になるんです」 皆はしんとした。若い英雄はうつむいて、そ こらの草の茎を摘んで、口にくわえた。 「ふうん、そんならあと何年かで、俺も貴様 の厄介になるわけだな」 その年はすでに太平洋戦争がはじまっていた。 ……このとき私に、たしかに一つの自覚が生じ たのである。暗い世界に大手をひろげて待ってい ること。やがては、五月の花も、制服も、意地悪 な級友たちも、私のひろげている手の中へ入って くること。自分が世界を、底辺で引きしぼって、 つかまえているという自覚を持つこと。……しか しこういう自覚は、少年の誇りとなるには重すぎ た。 誇りはもっと軽く、明るく、よく目に見え、燦 然としていなければならなかった。目に見えるも のがほしい。誰の目にも見えて、それが私の誇り となるようなものがほしい。例えば、彼の腰に吊 っている短剣は正にそういうものだ。 中学生みんなが憧れている短剣は、実に美しい 装飾だった。海兵の生徒はその短剣でこっそり鉛 9
筆を削るなんぞと言われていたが、そういう荘厳 な象徴をわざと日常些末の用途に使うとは、何と 伊達なことだろう。 たまたま、機関学校の制服は、脱ぎすてられ て、白いペンキ塗りの柵にかけられていた。ズ ボンも、白い下着のシャツも。……それらは花 々の真近で、汗ばんだ若者の肌の匂いを放ってい た。蜜蜂がまちがえて、この白くかがやいている シャツの花に羽根を休めた。金モールに飾られた 制帽は、柵のひとつに、彼の頭にあったと同じよ うに、正しく、目深に、かかっていた。彼は後輩 たちに挑まれて、裏の土俵へ、角力をしに行った のである。 脱ぎすてられたそれらのものは、誉れの墓地 のような印象を与えた。五月のおびただしい花々 が、この感じを強めた。わけても、庇を漆黒に反 射させている制帽や、そのかたわらに掛けられた 帯革と短剣は、彼の肉体から切り離されて、却っ て抒情的な美しさを放ち、それ自体が思い出と同 じほど完全で……、つまり若い英雄の遺品という 風に見えたのである。 私はあたりに人気のないのをたしかめた。角力 場のほうで喚声が起った。私はポケットから、錆 びついた鉛筆削りのナイフをとり出し、忍び寄っ 10